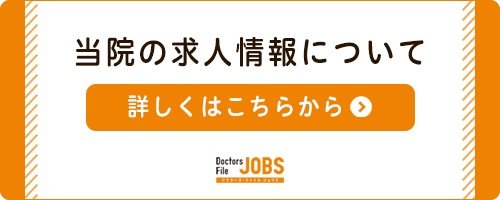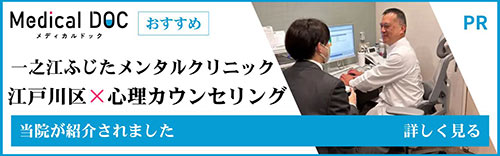躁うつ病とは
気分がハイテンションになる躁状態と気分がぐっと落ち込んでしまううつ状態の症状を繰り返していることを躁うつ病といいます。このように両極端な症状が、同一人物でみられることから双極性障害とも呼ばれます。躁からうつ、うつから躁へと変わる時期では、普通の状態になっていることが多いです。発症のメカニズムに関してですが、脳内の神経伝達物質の変化によるものと考えられていますが、変化の原因まではわかっていません。
躁状態について
なお躁状態とは、やる気に満ち溢れ、頭の中で次から次へとアイデアが浮かんでくるようになります。また睡眠を十分にとらなくても、活動的で衰え知らずのように見えます。このほか、早口でしゃべりまくる、怒りっぽくなる、集中力が散漫になる、衝動買いをするなどの浪費癖、異常に社交的になるといった症状がみられるようになります。
またうつ状態にある場合というのは、うつ病で見受けられる症状と同様で、気分が落ち込んでいる、何事にも興味が湧かない、疲れやすいなどの症状があらわれるようになります。
Ⅰ型とⅡ型がある
ちなみに躁うつ病は、躁状態がはっきりと出ている場合をⅠ型と言います。この場合、躁状態が1週間程度続くとされ、それによって日常生活に支障が及ぶのであれば、入院が必要ともいわれます。また躁状態が比較的軽く(軽躁状態)、その症状に本人も周囲も気づきにくいという躁うつ病もあります。これをⅡ型と言います。この軽躁状態は4日程度続くとされますが、その様子はわかりにくいです。なおⅡ型であれば全体的に症状が軽いということではなく、うつ状態は重く、その期間も長いです。
先にも述べましたが、躁の状態が確認しにくいと、うつ病との判別が難しいということもあります。ちなみにうつ病と躁うつ病では、治療内容が異なります。このことから当院では、丁寧な診察、より細部にフォーカスした問診を行うなどして、診断をつけていきます。
治療について
薬物療法と非薬物療法があります。薬物療法では、気分安定薬(リチウム 等)、もしくは抗精神病薬(アリピプラゾール 等)が用いられます。また非薬物療法では、病気について患者さんご自身が理解する心理教育、うつ状態にあるときは、否定的な考え方に偏りがちな思考や歪みを医師等のアドバイスで修正していく認知行動療法などを行っていきます。