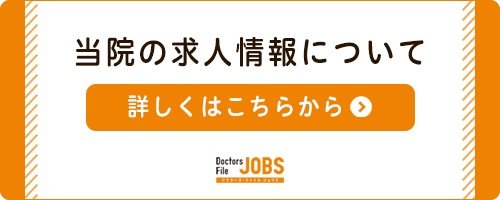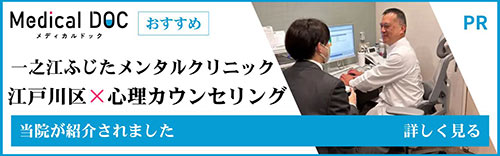パニック障害とは
パニック障害では、まず何の前触れもなく起きてしまうパニック発作がみられるようになります。同発作そのものは、長くても30分程度で治まるようになるのですが、その最中はとても息苦しく、動悸、発汗、めまい、胸痛などが現れ、死んでしまうのではないかと思うくらいの状態になります。そのような状況があったのにも関わらず、採血や心電図などの検査をしても異常がみられることはありません。
このように原因が特定できず、また患者さん自身で発作をコントロールすることもできないということもあるので、またいつパニック発作が起きるかという不安に襲われるようになります(予期不安)。そして、実際に発作が起きた際、人混みや密閉された空間で人に助けを求められない場所で起きたらという恐怖感を募らせてしまい、やがて外出そのものを控え、日常生活に支障をきたすようになります(広場恐怖)。このパニック発作、予期不安、広場恐怖の3つの症状がみられている状態にあるとパニック障害と診断されます。
同発作は、過労やストレスがきっかけになることがあるとされ、それが繰り返されるうちに不安や恐怖が生じるようになっていき、パニック障害につながっていくといわれています。
検査について
医師が症状を見ることで診断をつけることもあります。ただパニック発作の症状に似た病気というのもいくつかあるので、それらの可能性を除外するために採血、心電図、画像検査等が行われることも少なくないです。
治療について
パニック障害は、放置をすると症状が悪化するので治療が必要です。この場合は、薬物療法と精神療法が行われます。薬物療法は、パニック発作を抑制する目的で行われます。用いられるのは、抗うつ薬(SSRI)や抗不安薬(ベンゾジアゼピン系)です。
また薬物療法と併行して、精神療法も行っていきます。この場合、認知行動療法のひとつであるエクスポージャー法(曝露療法)が行われます。その内容とは、あえてパニック発作が起きやすい状況に身を置き、その環境に徐々に慣れていくことで、不安や恐怖を克服していくという内容になります。