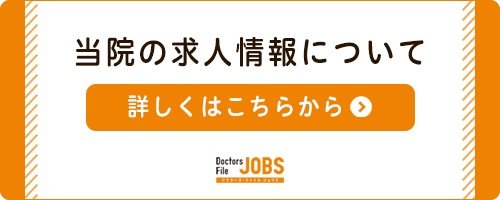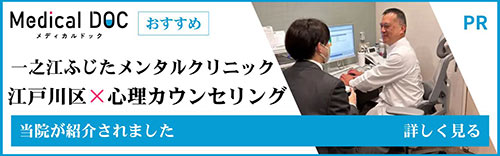睡眠障害
●睡眠障害とは
眠ることに対して、何らかの障害を抱えている状態が睡眠障害です。具体的には、寝付くことができない、眠れたとしても途中ですぐに起きてしまう、熟睡感がな、いなど様々な症状が含まれます。
その種類としては、日常的に最もよくみられ、同障害の中では最も患者数が多いとされる不眠症があります。また睡眠中、主に気道が閉塞してしまうことで、10秒以上の呼吸停止(および低呼吸状態)が睡眠時1時間当たりで5回以上はみられるとされる睡眠時無呼吸症候群(SAS)のほか、十分な睡眠時間をとっているのにも関わらず、日中も強い眠気に襲われるなどして、仕事や学習等が手に着かなくなる過眠症(ナルコレプシー、特発性過眠症、反復性過眠症)というのもあります。
また夜は眠り、日中は活動するという人々が持つ体内時計のことを概日リズムといいます。このリズムにズレが生じる(交代勤務、夜型の生活になる 等)などして、夜間にうまく睡眠がとれなくなる概日リズム睡眠覚醒障害も含まれます。このほかにも睡眠関連運動障害があります。その中には、布団の中に入って安静にしていると足がムズムズし、なかなか寝付くことができないむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)のほか、睡眠中の足に小刻みな震え等の付随運動が度々起こることで、目が途中で覚める、眠りが浅い等が起きるなどの周期性四肢運動障害も含まれます。
睡眠に関して悩みがある方で、上記のような睡眠障害の症状が見受けられる方は一度当院をご受診ください。
不眠症
不眠症とは
その人にとって必要とされる睡眠が充分にとれず、日中の生活時に様々な支障をきたしている状態にあると不眠症と診断されます。この場合、いずれも夜間の睡眠不足が原因となりますが、大きく4つのタイプに分けられます。
4つのタイプについて
その中でも最も多いとされているのが入眠障害です。同タイプは、布団に入って30分~1時間以上経過しても寝つくことができず、本人がそれによる苦痛を感じている場合に診断されます。
また寝つきは悪くないものの、夜中に何度も目が覚めて、睡眠が十分でないと感じる中途覚醒があります。これは不安やストレス、トイレに行きたくなるなどの身体的要因などが挙げられます。
さらに起床時間よりも2時間以上早く目覚め、それから眠ることができなくなる早朝覚醒というのもあります。このタイプは高齢者やうつ病患者に見受けられることが多いです。
上記のほかにも、睡眠時間をとっているにも関わらず、熟睡できていないと感じる熟眠障害もあります。この場合、加齢の影響で起きるというのも考えられますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)やむずむず脚症候群、周期性四肢運動障害によって引き起こされることもあります。
患者さんに見受けられる症状や訴えなどから、不眠症が疑われる場合は、問診や睡眠日誌をつけるなどしていきます。このほか、基礎疾患の有無を確認するための血液検査のほか、睡眠時無呼吸症候群の可能性をしらべるために簡易睡眠検査、PSGを行うこともあります。
治療について
不眠の原因が、何らかの病気によるもの等、特定しているのであれば、原因疾患の治療などによって取り除くようにしていきます。
上記以外では、睡眠薬を適宜使用する薬物療法を行うこともあります。また患者さんご自身がリラックスした状態をキープできる方法に努めることも大切で、自律訓練法やバイオフィードバック療法を取り入れ、心が穏やかになる方法を取得できるようにしていきます。
また生活習慣を見直すことも必要で、適度に運動をする、夕食後はカフェインの摂取を控える、一日三食を規則正しくとる、といったことなどもしていきます。また就寝前に興奮すると、覚醒しやすくなるというのも不眠の一因です。そのため、寝る前は心地よい音楽を聴くなどしてリラックスできる環境を整えていくこともしていきます。